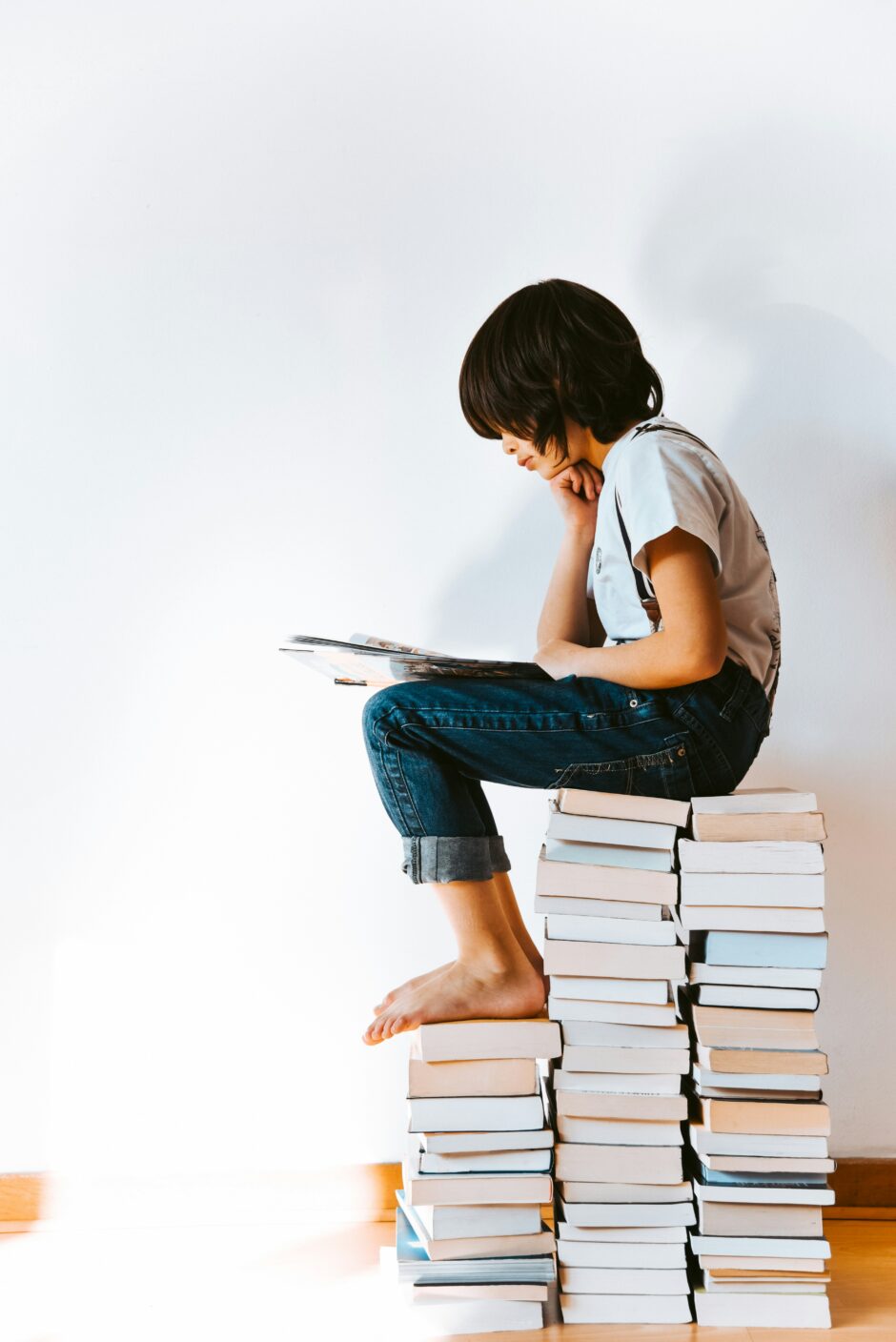なぜ働いていると本が読めなくなるのか(三宅香帆)
「大人になってから、読書を楽しめなくなった」「仕事に追われて、趣味が楽しめない」「疲れていると、スマホを見て時間をつぶしてしまう」……そのような悩みを抱えている人は少なくないのではないか。
「仕事と趣味が両立できない」という苦しみは、いかにして生まれたのか。
自らも兼業での執筆活動をおこなってきた著者が、労働と読書の歴史をひもとき、日本人の「仕事と読書」のあり方の変遷を辿る。
そこから明らかになる、日本の労働の問題点とは?
すべての本好き・趣味人に向けた渾身の作。(集英社ホームページより)

「本は心のご飯です」とは小学校の担任の先生の言葉。確かに食事と読書は似ている。どんな本を読んで心を育てるか。いや、心を育てる本を読めているか。そんなことが気になる人にお薦め。
お薦め度
格差と読書
働いているとか、働いていないとかの前に、本を読む人と読まない人ははっきり分かれている。どっちがいいとか、悪いとかではない。その辺は趣味の問題なのではないかと思っていたけれど、そこに社会の格差が存在していると作者は伝えている。読書の意思の有無が、社会的階級によって異なる。学ぶ動機付けを得られなかった者は「本なんて役に立たない」と思ってしまう。学ぶことに関心を持っている者はそれだけ恵まれている。
これはある意味そうだし、でもそれだけではないとも思う。僕も学ぶ動機付けが得られにくい環境で育った。でも、なぜか本は読んでいた。そして、1人でいろいろなことを考えていた。思考していたというより、妄想していた。何がきっかけになるかは分からない。読書から格差を超えるチャンスを得られるかもしれない。教養とか難しいことを考えず、食べたいものを食べるように、今読みたい本を読む。僕にとって最初の一歩が「本は心のご飯です」だったかもしれない。
全集と積読
昔の家には全集が置いてあった。箱入りの厚い本。今でいう鈍器本か。ずらりと並んでいると、なんだか教養がありそうに見える。全集は自分で読む本を選ばなくていい。お薦めを専門家がセレクトして、順々に届けてくれる。文学のサブスクのような状態だったのだろう。実家にもそれっぽい本は置いてあったが、ほとんど読まれていなかったはずだ。積読である。親の世代はとりあえず持っているのが格好いい的に買ったのではないか。
もっとも現代はもはや、それが格好いいとすらも思われないだろう。僕も全集は持っていない。本棚には雑多な本が整理もされずに並んでいる。教養は、あまり感じない…。
情報と知識の違違い
「読書離れ」「活字離れ」の議論が出ると、「いや、本は読んでないけれど、インターネット記事は見ている」という反論が上がる。ある意味、正しいし、ある意味ずれている。本書では情報と知識の違いを説明している。情報は知りたいことだけを純粋に絞ってたもの。直接的に入ってくるもの、使えるものである。インターネットやSNS、動画などで得られるのはほとんど情報だ。一方、知識は知りたいことにプラスして一見関係のないようなノイズが混ざっている。過去や歴史、文脈はノイズ。それがあってこそ、思考が深まるのだが、そんなこと知ったこっちゃないという人が増えている。
新聞に求められるのは基本情報だ。スッと読めるようにノイズを除去することを求められる。限られた紙面ではやむを得ないが、もっと知識とつながる紙面も作れないか。改めて考えさせられた。
自分で自分を搾取
本書は読書の歴史を紐解くとともに、働き方の歴史も詳しく解説している。全身全霊で働いていては読書をはじめ、趣味や家庭の時間がとれないというのは、まあその通り。週休2日で働いたことのない僕にとっては、それだけ休みあれば何とでもなるのでは?と思ってしまうが、その辺はひとそれぞれ。会社の働き方改革で、読書の時間を取り戻す、とは簡単にいかないという点は同意できる。
「自分はもっとできる」。新自由主義は自己責任と自己決定を重んじる。自ら戦いにのぞむ。その先には疲労がある。疲労社会である。自分で自分を搾取する働き方が定着している。「働き方改革」は働き方を選べるもので、働きたい人がどんどん働ける環境をつるくのも改革の一つだろう。それでは、疲労社会は止まらない。
本は食事と違って、絶対にとらないといけないものではないけれど、本好きがどうやってその時間を確保するか。結局、ビジネスに直結する情報を生かして財をなし、ファイヤーするしかないのか。この本でも解決策は見いだせていない。
編集後記
読書離れとはいうけれど、このタイトルが受けるということは、本を読みたい人がまだまだいるということ。「仕事とスマホで毎日を終えたくないあなたへ」のコピーも秀逸です。僕自身は全身全霊で働きすぎなのかなと反省しつつ、そうでないと仕事ではないとも思い。まだ解決には至っていません。
 本の処方箋 熊野堂
本の処方箋 熊野堂